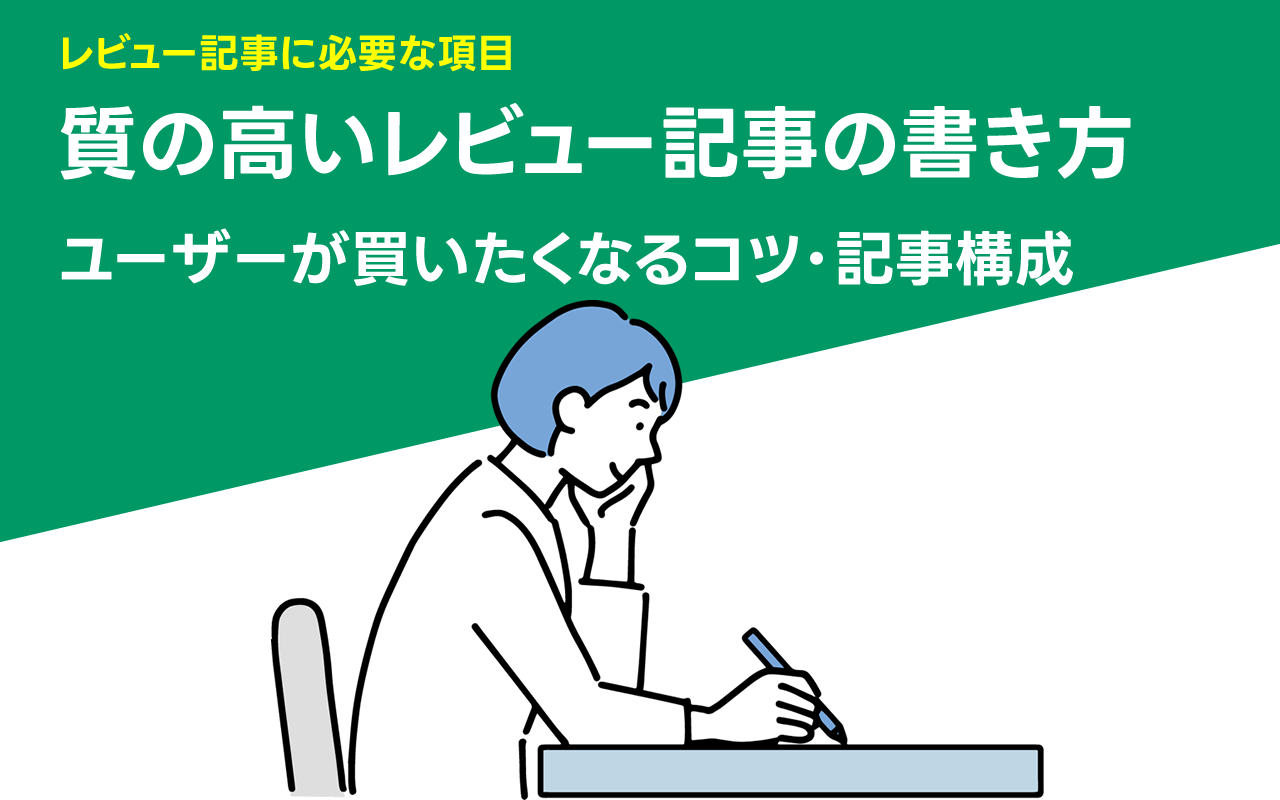レビュー記事で「商品情報以外に、何を書けばいいのか分からない」ということで悩んでしまうことはありませんか?
商品情報は、公式販売ページにものっているので、それだけのせても意味はありません。
「ユーザーがレビュー記事に期待しているのは何か。」
「レビュー記事には何を書けばいいのか。」
この記事では記事前半で、レビュー記事に必要な項目やコツを、後半ではユーザーが買いたくなる記事構成について解説します。
Contents
レビュー記事に必要な項目
レビュー記事に必要な項目は、Googleが提唱している「質の高いレビューを書く方法」から読み解くことができます。
質の高いレビュー記事に必要な項目
主要なものをピックアップすると下記のようになります。
- ユーザー視点で商品を評価する
- 商品に対する知識が豊富であることを示し、レビューの信頼性を裏付ける証拠を提示する
- 商品を定量的(数値・数量で表す)に測定したデータを提示する
- 競合商品と比較する
- バージョンアップによる違いを比較する
- 複数の商品を提示して、商品の特長と最適な利用シーンを説明する
- 商品のメリット・デメリット
- 商品の選び方
- 複数の販売者へのリンクを提示して、ユーザーが選択できるようにする
参照:質の高いレビューを書く
全ての項目を追加できれば、それだけ質の高い記事が作れますが、難しい場合は書ける項目をピックアップして使いましょう。
レビュー記事を書く時のコツ
前述の項目は、記事の質を高めるためのものであって、ユーザーに行動(購入)してもらうためのものではありません。
商品を購入してもらうには、ユーザーに行動してもらう必要があります。以下から、そのコツについて説明します。
「それがほしい」と思ってもらうにはどうする?
商品を購入してもらうのには、「その商品がほしい」と思ってもらるかどうかが重要になります。
ユーザーが「その商品がほしい」と思うのは、「ベネフィットをイメージできた時」です。
「ベネフィット」とは、ユーザーが商品やサービスを購入した後に得られる「満足感・幸福感」のことで、これを感じた時に「商品がほしい、または買おう」と思うようになります。
例えば、下記のような感じです。
【悩み】
毎日食器を洗うのは面倒。水も冷たいし、手も荒れるし。何より時間が無駄。
【ベネフィット】
面倒な食器洗いから解放され、手荒れもなくなり、自分で洗わなくていいので、自由時間が増えます。
「そんな商品・サービスがあるならほしい」と思いません?これがベネフィットです。
ユーザーの「悩み」とそれに対する「ベネフィット」を見つけることができれば、ユーザーに行動(購入)してもらうことができます。
両方を見つけるのに役に立つのが「ペルソナ」です。
ペルソナを作成して、その人が「どういうことに悩んでいるのか」「何を提供すれば問題解決できるのか」「そこから得られるベネフィットは何か」を考えましょう。
| 悩み | 食器を毎日洗うのは面倒。水が冷たい。手が荒れる。洗っても洗っても終わらない。時間が無駄。 |
| 解決策 | 食器洗浄機 |
| ベネフィット | 面倒な食器洗いを自分でしなくてよくなる方法があります。寒い時期によくあるあかぎれ・ひびわれがなくなり、何よりも自分で洗わなくていいので、自由時間が増えます。 |
「五感」を刺激する文章を書く
商品情報は、淡々と書くのではなく、ユーザーに伝わるように「五感」を刺激する文で書きましょう。
「五感」を刺激するとは、文章に「形容詞」や「オノマトペ」を使うことです。
| 五感 | 表現方法 |
| 視覚 | ・キラキラしている ・目がチカチカするような明るさ ・真っ赤なリンゴ |
| 聴覚 | ・ギャーギャーとうるさい ・シーンとしている中で ・ポタポタと水がしたたる |
| 味覚 | ・ハチミツのようなあまさ ・コーヒーのような苦み ・シロップのほんのりした甘さ |
| 嗅覚 | ・焼きたてのパンのような香り ・鼻にツーンとくるワサビの辛さ ・生ごみのような臭い部屋 |
| 触覚 | ・ふんわりととろけるスポンジケーキ ・納豆のようにねばねばしている ・ザラザラした手触り |
五感を刺激しない例文と刺激する例文がこちら。
✕ 五感を刺激しない例文
このスマートフォンは、滑り止めのコーティングが施されている。手に収まるサイズで持ちやすい。見た目は黒くて高級感がある。
〇 五感を刺激する例文
このスマートフォンは、機体表面にザラザラした滑り止めのコーティングが施されている。手の中にすっぽりと収まるサイズで持ちやすい。見た目は真っ黒で高級感がある。
前者は必要最小限で書いた文で、後者は「真っ黒」という形容詞や「ザラザラ」「すっぽり」といったオノマトペを使って、「商品の状態が分かる」ように書きました。
どちらの方が、五感を刺激されましたか?おそらく後者だと思います。ウェブの文章は「読み飛ばされることが多い」のですが、読み飛ばす人をターゲットにして書くと、じっくり読む人に伝わりません。
そのため、レビュー記事は「じっくり読む人」に向け、形容詞やオノマトペを使って、伝わるよう文を作りましょう。
なお、オノマトペ(擬音語・擬態語)は、幼稚な印象を与えることがあるので、多用は禁物です。
レビュー記事の構成
ここからは、前述のレビュー記事に必要な項目を使った「レビュー記事の記事構成」について説明します。
レビュー記事の構成
- 1)商品についての知識をアピールする
- 2)この商品を購入した理由
- 3)商品の詳細(スペック)
- 4)商品のメリット
- 5)商品のデメリット
- 6)口コミ
- 7)自分が得られたベネフィット(まとめ)
- 8)ユーザー選択可能な商品へのリンク
1)商品についての知識をアピールする
レビュー記事のリードコピー(またはプロフィールページに記載してリンク)に、商品に関する「自分の知識量」を紹介しておくと専門性をアピールできます。
単純に、専門知識がある人のレビューの方が信頼できるからです。これは、Googleが推奨しています。
「自分が商品を利用した期間」を専門性としてアピールするのであれば、できるだけ長いほうが知識量が多いイメージを与えられます。
期間が短い場合は「短いことを武器」にする書き方が必要です。
例えば「1週間使っただけでも変化が分かる!〇〇を使ってみた感想を正直レビュー!」というような書き方にすれば、期間が短くてもインパクトを与えられます。
ただし、あまりにも短い期間(1日や2日)は「本当に使ったの?」と思われてしまうので、武器にはなりません。少なくとも1週間くらいは、とことん使ってからレビュー記事を書きましょう。
この他、その商品だけでなく、同じカテゴリーの利用履歴なども専門性のアピールにつなげられます。例えば「Androidユーザー歴10年のぼくがiPhoneを使って感じたメリット・デメリット」みたいな感じで書くこともできます。
2)この商品を購入した理由
商品を購入した理由の書き方には、主に「問題解決タイプ」と「使用感タイプ」があります。
「問題解決タイプ」は、「何に困っていたのか」や「何を解決するために購入したのか」のような共感を引き出すための書き方です。
困っていることや問題となっていることを具体的に書くことで、同じ悩みを持っている人に興味を持ってもらえます。
「使用感タイプ」は、実際に商品を使ってみた「使用感」や「嬉しかったこと」を伝える方法です。
これらは、商品やサービスを購入するうえで重要な情報になり、商品の魅力を伝えることができます。
「安いから購入した」というような商品メリットは、ユーザーに行動してもらう理由としては弱く、魅力的ではないため、「問題解決」や「使用感」を使って、共感や魅力を伝えられる文章にしましょう。
3)商品の詳細(スペック)
2)で商品に興味を持った人は、どういう商品を買って、悩みを解決できたのかを知りたいはずです。
そのため、ここで購入した商品の基本的な情報やスペックを書いておきます。
競合商品と比較したスペック表があれば追加し、比較した結果「なぜ、この商品を選んだか」「どこが良かったのか」をおおまかに説明すれば、次の詳細説明(商品メリット)へと、つなげやすくなります。
4)商品のメリット
商品のメリットでは、実際に利用して感じた特長を、画像・動画・音声などを使って、分かりやすく説明します。
ここが「五感を刺激する文章を書く」パートです。また、画像や動画などの見る情報は、文字以上に多くの情報をユーザーに伝えられるので、さまざまな角度からとった写真や動画があると魅力的な記事になります。
ただし、無駄に大量の写真をのせるのではなく、ユーザーの気持ちになって「どういうことを知りたいか」を意識して撮影しましょう。
動画の編集には時間がかかるので、編集したくない場合は、事前に撮影手順を考えておき、その流れにそってスマートフォンで撮影すれば、編集せずにすみます。ただし、うまくいくまで何回か撮りなおしは必要です。
撮った動画をツイッターやインスタグラムにアップロードすれば、それを記事に埋め込んで使えます。
5)商品のデメリット
使い始めは感動で「メリット」しか見えませんが、使い込んでいるうちに、物足りない部分が見えてきます。
それをデメリットとして書きましょう。
デメリットを書いたら、その解決方法もセットで書くことが重要です。問題が起きても解決できるという安心感を与えられます。
6)口コミ
ここまでの記事は、主観(自分の意見)で書いているので、客観的な意見を取り入れるために第三者の口コミを使いましょう。
口コミとして使えるのが、ツイッターやインスタなどのSNS投稿です。埋め込みタグを使えば、内容をそのままブログに「引用」できます。
ユーザーに正しい情報を伝えるために、口コミを掲載する時もメリットとデメリットの両方をのせましょう。
7)自分が得られたベネフィット(まとめ)
最後に、自分が得られた「ベネフィット」をガッツリ書きます。
「ベネフィット」は、商品・サービスを使ったことによって、自分が得られた「満足感」です。
この商品を使うことで「何が解決できて、どう感じたか」を分かりやすく書きましょう。
8)商品リンクを選択可能にする
商品への誘導リンクは、複数用意して、ユーザーが選択できるようにしましょう。Googleも複数の選択肢を推奨しています。
例えば、Amazonだけでなく、楽天市場やYahoo!ショッピングも選択肢に加える、ということです。
WordPressで「Amazon」「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」の3つのリンクを作るなら、プラグインを使うと便利です。
これらのプラグインは「Amazonアソシエイト」「楽天アフィリエイト」「バリューコマース」のAPIを使って、アフィリエイトリンクを作成しているため、利用するにはASPに登録してAPIキーの取得が必要です。
なお、商品リンクは、記事の最後だけでなく、記事の上にも表示させましょう。例えば、「3)の商品の詳細」に設置すれば自然な感じになります。
補足)特典があれば紹介する
もし、割引などの特典があれば、それも記載しましょう。迷っているユーザーの気持ちを後押しできます。
特典情報は、記事の後半だけでなく、前半にも表示させて、特典を知らずに離脱してしまうのを防止し、最後まで読み進めてもらう動機を作りましょう。
特定の商品を最もオススメする時のレビュー方法
自社商品を「一番のおすすめ」として販売したい場合、ランキングを作って自社商品を一番にすると不自然です。
そういう場合のレビュー記事の作成方法について紹介します。
オススメする根拠を体験を元に説明する
その商品が一番だと考える根拠を、体験を元に説明しましょう。
体験したことで、得られた知見を使えば、信ぴょう性が高くなります。Googleの「質の高い記事を書く方法」にも記載されています。
そのために必要なのが下記の作業です。
- 1)自社商品を徹底的に利用する
- 2)他社商品を徹底的に利用する
- 3)他社商品との違い・搭載していない機能を見つける
違いを見つけて、それを自社商品の強みとして掲載できないか考えてみましょう。他社商品が搭載していない機能や特典があれば、それは自社商品の強みになります。
もし、たいした違いが見つからなくても、それを「言い回し」で強みにできないかを考えましょう。
「言い回し」で強みにする場合に重要なのが、競合視点ではなく、ユーザー視点で考えることです。何に悩んでいて、自社商品の小さな強みが「ユーザーのどの悩みを解決できるか」を考えてください。
まずは、徹底的に自社と他社商品を利用して、違いを見つけることです。
レビュー記事用のテンプレート
レビュー記事に必要な項目や構成をテンプレート化して利用すれば、構成に時間をかけなくてすみます。
記事構成テンプレート
レビュー記事用の記事構成テンプレートは、下記のようになります。
「必要な項目」「見出し名称」「順番」は、状況に応じて追加したり、入れ替えたりしましょう。
| 項目 | 主な構成要素 |
| ①商品についての知識をアピールする | ・商品に対してどれほど詳しいか ※リードコピーの最後に書く |
| ②この商品を購入した理由 | ・悩んでいたことや困っていたこと ・使い勝手や嬉しかったこと |
| ③商品の詳細(スペック) | ・商品の基本的な情報 ・競合商品との比較表 ・商品リンク(アフィリエイトリンク) |
| ④商品のメリット | ・商品のメリットを画像・動画を使って説明する ※五感を刺激する |
| ⑤商品のデメリット | ・商品のデメリットとその対策 |
| ⑥口コミ | ・SNSを使った第三者のリアルな口コミ |
| ⑦自分が得られたベネフィット(まとめ) | ・自分が得られたベネフィットを書く ・商品リンク(アフィリエイトリンク) |
エアーレビューとは?
エアーレビューとは、実際に商品やサービスを購入していないにも関わらず、購入して使ったかのような感想やレビューを投稿することです。
同じような商品を持っていたり、第三者が投稿したレビューを見たりすれば、ある程度予想がつくため、エアレビューは不可能ではありません。
エアーレビューはやらない方がよい理由
エアーレビューでは、かなり調査しないと、商品の深いところが書けず、記事の内容も薄っぺらくなってしまいます。
また、実際とは異なる情報を提供してしまったり、お問い合わせに答えられなかったり、自分の信用を失ってしまう可能性もあります。
結局、ユーザーには伝わらないレビュー記事となってしまうため、エアーレビューはやらない方がいいです。
だがしかし・・・
とはいったものの、実際エアレビューをやっている人は多いです。
アフィリエイトの単価が高いものは、販売価格も高くなり、それを毎回購入して、レビュー記事を書いていたらきりがありません。
そういう場合の対策としては、下記のものがあります。
- ①無料の範囲を使って想像する
- ②ChatGPTなど生成AIを使って文章を作成する
- ③お試し期間を使って確認する
- ④利用した人にインタビューする
- ⑤ライターに記事を書いてもらう
①と②に関しては、ユーザーに間違った情報を与える可能性があるのでやらない方がいいです。
③に関しては有料版を自分で試すことができるので、このお試し期間を最大限に活用することで、信頼性の高い記事を執筆できます。なお、お試し期間が短い場合は、事前にできる限り調査をしておくことで、効率よくネタを集められます。
事前の調査でやることには下記のようなことがあります。
- 商品で利用できる機能を抽出して、お試し期間中に全て利用する
- 競合商品との差別化ポイントを調べておき、本当に差別化できてるかを確認する
- 使い方が分からない部分を調べておき、画像や動画で保存する
④と⑤は自分が利用していないので、あいまいな部分がでてくる可能性がありますが、インタビューの内容や指示の仕方によって①や②よりも完成度が高くなるのでこれらの利用もおすすめです。
レビュー記事に使う商品はどうやって用意する?
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのセールを利用して商品を購入すれば、比較的安く商品を購入してレビュー記事が書けます!
Amazonならタイムセール祭、楽天市場ならお買い物マラソン、Yahoo!ショッピングなら超PayPay祭などのセールがあります。
セルフバックでレビュー記事を書く
また、セルフバック商品を利用して記事を書くこともできます。
「セリフバック」は、商品やサービスを自分で購入しても「成果報酬が発生する仕組み」です。
試してみたい商品やサービスを通常より安く購入したり、体験したりできます。
※全てのアフィリエイト商品がセルフバックの対象ではありません。
まとめ:レビュー記事に必要な項目と構成
以上、レビュー記事を書く時の「コツ」「項目」「記事構成」について紹介しました。
レビュー記事を書く時は、ユーザーが「ほしくなる瞬間」を考えて、「五感」を刺激する文章を書きましょう。
必要な項目と記事構成は下記のようになります。
レビュー記事に必要な項目
- 1)商品についての知識をアピールする
- 2)この商品を購入した理由
- 3)商品の詳細(スペック)
- 4)商品のメリット
- 5)商品のデメリット
- 6)口コミ
- 7)自分が得られたベネフィット(まとめ)
- 8)ユーザー選択可能な商品へのリンク
項目や順番は、必要に応じて追加したり、入れ替えたりして最適な記事構成にしましょう。